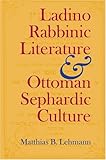| ロックミュージックの社会学 (青弓社ライブラリー) 南田 勝也 青弓社 2001-08 売り上げランキング : 261052 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
最近は社会学・音楽学の本を手に取ることが多いのですが、これもその中の一冊。
勿論自分自身は専門ではないので読んで「ふうむ」とか思うくらいなのですが、この本は「ふうむ」に終わらず、随分興奮しました。10代の頃からの自分の「ロック」分析とその歴史の記述と基本線において軌を一にし、さらには自分自身の目の届かないところも(当たり前ですが)キッチリと俎上に乗せてくれているからです。
自分自身は、今となってはそこまで「ロック(ミュージック)」に思い入れがないのですが、大多数の若者と同じ程度かそれ以上には聴いてきた・関わってきた経験があります。
それまでも巷の流行曲やゲームのサントラなんかにも親しみはあったのですが、そもそも真面目に音楽に対して向かい合い始めたのは、おそらく中学生の頃からでしょうか。もう遙か時の彼方なので少し自信がないのですが、中一の頃に10歳ほど年上の友人にもらったzabadakを聴いてから、「音楽」という存在のウェイトがぐっと増したような記憶があります。その後遅ればせながらX(定番ですね。まだ現役でした)を聴き始め、「ロック」というものを強く意識し、音楽遍歴が始まった気がします。その後中二の頃に家のレコードプレイヤーから流れてきたQueenの「Bohemian Rhapsody」とカルメン・マキ&OZの「私は風」に度肝を抜かれ、「ロック」遍歴は始まったのでした。
前者によってプログレ(ッシブ・ロック)の扉が、後者によってHR/HMの扉が開かれ、中三の終わり頃からは主に前者の道に進むことになるのでした。後者はともかく前者については音楽的嗜好を共通とする友人はほとんどおらず、孤軍奮闘でしたが…。
音楽遍歴について書き始めるときりがないのでまたの機会に。
言いたいことは、自分は「ロック」なるものを多少なりとも聴いてきた。その経験から「これはロックである」「これはロックでない(ポップだよ)」等の判断を自覚的無自覚的に下している。つまり「ロックを語る(判断する)場」に参加している──ということです。
本書は全7章ですが、大きく前半(1〜3章、4〜終章)と後半に分けることが出来ます。
前半の第1章 ロックミュージック文化の三つの指標、第2章 ロック<場>の理論、第3章 ロック<場>の展開、は、社会学の理論に基づいて欧米文化発の「ロックミュージック」及びその<場>を分析・史的記述したもの、第4章〜終章 日本のロック─60、70、80、90年代、は欧米文化発のロックが日本においてどのように受容・展開されたかを記しています。
全章が興味深いので、順番に。
第1章では1960年代中期から後期にかけて「ロック(≒ロックンロール)」なるものを成立させる要素及び「ロック」であることを決定づける価値観の体系を、
①社会的布置での「下方向」志向を意味する、<アウトサイド>指標
②純粋芸術へ挑戦し続ける、<アート>指標
③ポピュラリティを獲得していく、<エンターテイメント>指標
として提示します。
この「ロック」成立時の60年代中期から後期にかけては、世界的な対抗文化のうねりの中、偶有的にこの3つが相互矛盾することなく渾然一体となった瞬間であり、後に「ロック」の原風景として参照されることになります。
この三つの指標のうち個人的に面白いなと思ったのが、③の<エンターテイメント>指標です。ロックの前身は当然ながらロックンロールですが、そのロックンロールはエンターテイメントに大きな比重が置かれていました。ロックはポピュラリティを捨て<アート>に特化していくジャズとは違い、自身をある一定層(若者やマイノリティ)を代弁するものであるとする傾向がありますが、そのような自己認識もあって、ロックンロールの正当な嫡子である(と自認する)ロックはエンターテイメントを捨てなかった。
この<エンターテイメント>指標に関連するものとして、商業主義の問題があり、後に二つの指標と激しく争うことになります。「商業ロック」や「飼いならされたロック(=ポップ化)」として批判されるような問題です。ですが、この60年代中期から後期にかけての時点では対抗文化自体が独自の流通システムを用意していたため、そのシステムに乗るならば大資本が独占する流通ルートを使わずに済む=<アウトサイド>性を確保できるため、問題にならなかったと解説します。なるほど。
第二章はブルデューの<場>理論を用いて「ロック<場>」という分析装置の構築に向かいます。その目的とするところは「何をもってロックとするのか」「どのような社会的ポジションをロックと感じるのか」という曖昧模糊とした質問に答えることです。
本書の図表(p. 59、圧巻!)を見れば大体は理解できるのですが、ここでは高級音楽芸術(≒西洋クラシック)<場>とロック<場>を垂直軸・社会空間(上流・中間・下層)に中心点を共有する三角形として合わせ鏡のように布置し、横軸には前者においてはピュア・アートとインサイド指標をとり、後者においては<アウトサイド>指標と<アート指標>をとります。中心点には大衆化<エンターテイメント>指標を置き、商業主義・消費社会の要請としての文化的正当性の異化・無化を、全体と合同する四角形として置きます。
試しに文章にしたらさっぱり分からない(幾何学はダメです)ので、買って見てみてください。
しかしこれは異常に優れた図です。
この「ロック<場>」が如何に優れているかということは、次章以降の<ロック>史(≒ロック史)の記述で明らかになります。
さて第三章は承前の分析装置を用いて<ロック>史を記述していきます。
70年代に入り対抗文化や学生運動は下火となっていきますが、それに呼応するかのように「ロック」の狂騒も下火となり(ビートルズも解散しますね)、70年代中期までに「ロック」の分化が起こります。
「分化」とは、上記三指標のいずれかにウェイトを置き・置いてるとみなされ(勿論他の指標を排除するというわけではない)、それが「ジャンル」として成立していくプロセスを意味します。
<アウトサイド>指標を志向した「ロック」は、60年代末の対抗文化の衰退を受け、この時期「穏当なるアウトサイダー」として振る舞い、中央文化に対する「周辺文化」を基盤とした「ロック」を創り出した、と述べます。彼らの向かう先は(アメリカでは、という限定があった方がいいと思います)「土」「郷愁」といったものを感じさせるジャンル、つまりサザンロックやカントリーロックと名付けられます(デュアン・オールマン華やかりし頃のオールマン・ブラザーズ・バンドの活動時期やザ・バンドを思い起こしましょう)。以上はアメリカでの話ですが、イギリスではグラムロックがこれに当たるとのこと。グラムロックが<アウトサイド>と言うのは少し意外の感がしますが、確かに通常の社会通念の埒外(「ジギー・スターダスト」に至ってはもう異星人です)に存在している、というパフォーマンス(設定)はそうですね。著者はこの70年代前半という対抗文化挫折の時期に<アウトサイド>指標を強く志向するグラムロックがこのようにアウトサイダーを「戯画化」して演じてみせるのは非常に象徴的だと述べます。
<アート>指標を志向したグループは、「ロック」を高級芸術音楽と同等の地位にまで引き上げようとし、音楽理論を駆使し、技巧を凝らし、ちょうどクラシックの分野で現代音楽が試みたようなことをし始めます。後に「プログレッシブロック」と呼ばれるジャンルです(思えばクリムゾンの1stアルバムがアビーロードをチャートから蹴落とした(という話)のも69年も終わりに差し掛かる頃です)。彼らは「芸術」としての「ロック」を追求していったがために、それはロックンロールの系譜である「踊る」ための<エンターテイメント>から、「聴く」ための<アート>へと強く志向することになります。確かにこの頃のプログレのコンセプトアルバム(思いつくまま適当に挙げましょう。「海洋地形学の物語」「The Snow Goose」「A Passion Play」「狂気」)なんかを聴いてると、エルヴィスやチャック・ベリーの直接の嫡子とはもう思えませんよね。ロックは第一に<エンターテイメント>である、と考える層にとっては、もうこれらの音楽を「ロックである」と言うのに躊躇してしまうかも知れません。受容者層の分断化が見てとれそうです。
<エンターテイメント>指標を目指したグループはその後どのようにジャンル分けされるのかというと、ここで出てくるのがハードロックだと述べます。オジーのパフォーマンスやディープパープルのライブアルバムの盛り具合、クイーン来日時の狂騒などを思い出すと、確かに彼らはまずプロの「エンターテイナー」であるというような気がします。
勿論、前にも少し注意書きを入れましたが、この三つの指標のうち一つ「のみ」に特化するということは妥当ではありません。イエス・ソングスやオールマンのフィルモア・イーストを聴いていると彼らのライブは超一流のエンターテイメントですし、ツェッペリンやクイーンの音作りは確実に<アート>を志向しています(だからこそ「ジャンル分け」が難しいのですが…)。
しかし著者によるとこのハードロックの<エンターテイメント>志向の流れはエアロスミスやキッス等(おお、彼らはデビューする頃にはもう70年代中盤に差し掛かろうとしています)を想起すると、もうその頃にはハードロックは<エンターテイメント>指標を代表するロックの下位ジャンルと認識されるようになっていた、とのこと。
(そう考えると73年デビューのクイーンの<エンターテイメント>と<アート>の両立(してると思ってます)が際立ちますね)
以上ここまでが、パンク出現以前の<ロック>(=まだ「ロック」)の状況です。
個人的にはロックンロール発祥の地・アメリカとイギリスを引っ括めて考えて良いのかなという気がしないでもないですが、なかなかに興味深いですね。
今思いついたのは、カンサスのロビー・スタインハート(Vn.)がインタビュアーに「あなた達の音楽はプログレだって言われてるけど?」と質問された時、「いや〜、ロックンロールだろ〜」と答えたという話です。自分は常々彼らを「プログレ」に分類することに違和感を感じていたのですが、彼らは(少なくともロビーは)エンターテイナーとして自分たちを位置付けていたんですね。彼らは初期(2ndまでが特に)は南部をルーツとした音作りをモロにしており、そういう意味ではサザンロックに分類されるのですが、ロビーのヴァイオリンと変拍子の多様、演奏能力の高さと凝った曲構成のせいで<アート>指標が強いとされ、プログレに分類されているのでしょう。ただ二回ライブに行った身として、また先のロビーの返答を受けて、サザンロックかハードロックに入れてあげたいですね。
さてこの時期<アウトサイド>指標に分類される「ロック」は、明らかに既成の価値観への挑戦や反骨精神といったものを欠いたように見えるのですが(正直自分にも<エンターテイメント>との違いがほとんど見えないくらい「薄い」)、それは当時「ロック」に「アウトサイダー」としての役割を期待する層からしてもそうだったようで、70年代後半に入った頃に「アウトサイダー」による「ロック」奪回が起こります。
言わずもがな、パンクです。
長くなったのでまた次回に。ちょっと気合入りすぎました。